皆さん、こんばんは!(こんにちは)
テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」(火曜・午後7時)の2025年2月4日放送回では、「大人気回転寿司チェーン店で“言われてみたらフシギ”を大調査!ガリの江戸時代の意外な使い方とは?スタジオに回転寿司レーンも登場で一同大興奮!」という内容です。
MC:出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋。
おもしろいメンバーですね。
番組では、江戸時代のガリの意外な使い方、くら寿司の皿投入口が誕生した理由など、フシギを解き明かしていきますよ。
とくに筆者が気になったのは、ガリです!
ガリのフシギを調べてみました。
ガリは江戸時代にどのように使われた?おしぼり代わり?
 ガリの使われ方とは?
ガリの使われ方とは?
ガリは、新鮮な生姜を薄切りにして甘酢で漬け込んだ日本の伝統的な食べ物です。寿司屋で必ず見かけるこの食材。ガリという名前は、食べた時の「ガリガリ」という食感から来ていると言われています。
ガリが寿司屋で使われ始めたのは江戸時代とされていますが、考えたら、不思議ですね。
なぜガリが添えられるようになったのでしょう。
 寿司にはガリが添えられる
寿司にはガリが添えられる
当時から寿司のそれぞれの風味を引き立てるため、提供されていたそうです。
これには理由があります。
寿司は生魚ですから、まず食中毒を防ぐ目的がありました。
ショウガに含まれるジンゲロールという成分に、殺菌効果が期待できると言います。
他にも、がん予防に効果的なショウガオールという成分や免疫力アップ作用のあるファイトケミカルも含まれている食材なんですね。
江戸前寿司は元々は屋台形式。せっかちな江戸っ子がさっと食べるファーストフードのような寿司でした。手づかみで食べる風習があるのもそのためです。
手で食べるとシャリが指にくっついてしまいますね。
高級寿司店などではおしぼりが出てきますが、江戸っ子はおしぼりなんて使いません。
ガリで指を濡らしながらお寿司を食べていたらしく、ガリはおしぼり代わりだったとか。
なるほど。時代が生み出した知恵でしょうか。
アガリとナミダにも意味が…
お寿司屋さんではお茶をアガリと呼び、わさびをナミダと言います。
お茶に含まれるカテキンには、身体に入った添加物が発生させる活性酸素の害を抑えてくれるらしい。
わさびは、食中毒の病原菌に対抗できる効果が古くから認められていますね。
ガリ、アガリ、ナミダ。これらは寿司を安全においしく食べるためには欠かせないってわけ。とくにガリの使い方は意外でした。
回転寿司のフシギな「お皿投入口」
回転寿司では「お皿投入口」が今やお馴染みです。今ではどの店舗でも見られるこの仕組みですが、フシギです。
これ、誕生のきっかけはお客さんの声だったのです。
「お皿を積み上げるのが恥ずかしい」や「大食いに見られるのが嫌」「テーブルの上が散らかるのが気になる」など。最初はいろいろと不満があったようです。
そこで「お皿投入口」が開発され、お皿はすぐに片づけられるようになったんですね。
まとめ
本日はテレビ「フシギの会」から、お寿司のガリについて気になったのでまとめてみました。いろんな歴史があるものです。回転寿司の歴史もいろいろありますし、世の中はフシギ尽くしとも言えます。
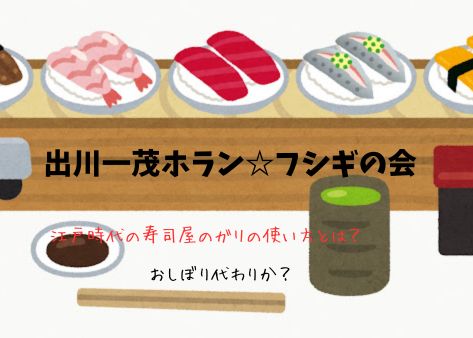
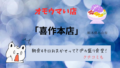

コメント